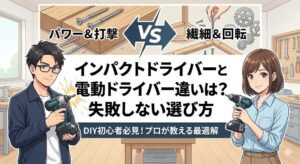解体作業や庭木の剪定で活躍する電動工具、レシプロソー。しかし、「レシプロソーとは具体的にどんな工具?」「セーバーソーやジグソーとの違いがわからない」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
また、レシプロソーの選び方や使い方にはコツがあり、何に使うかによって最適な替え刃の種類も変わってきます。さらに、レシプロソーがチェンソーやジグソーの代わりになるのか、そしておすすめのメーカーはどこかなど、知りたいことはたくさんあるはずです。
この記事では、そうした疑問を解消するため、レシプロソーの基本から応用まで、専門的な知識を分かりやすく解説していきます。正しい知識を身につけ、あなたの作業をより安全で効率的なものにしましょう。
- レシプロソーの基本的な定義と主な用途
- セーバーソーやジグソー、チェンソーとの明確な違い
- 作業内容に応じた最適なレシプロソーの選び方と替え刃の種類
- 初心者でも安全に使えるレシプロソーの使い方のコツ
レシプロソーとは?基本を徹底解説
- まずは基本!レシプロソーとは?
- レシプロソーとセーバーソーの違いは?
- レシプロソーは何に使う?主な用途
- レシプロソーで切れるもの一覧
- レシプロソーはジグソーの代わりになる?
- レシプロソーとチェンソーの違いを解説
まずは基本!レシプロソーとは?

レシプロソーとは、細長いノコギリ刃(ブレード)を前後に往復運動させることで、様々な材料を切断する電動工具です。「レシプロケート(reciprocate)」という「往復運動する」を意味する英単語が名前の由来となっています。
手ノコギリに比べて圧倒的に速く、力もいらずに材料をカットできるのが大きな特徴です。主に、丸ノコのような回転系の刃物では作業しにくい場所や、精密さよりも切断スピードとパワーが求められる場面で活躍します。
レシプロソーの主な特徴
刃が前後に動くシンプルな構造のため、丸ノコなどで起こりやすいキックバック(刃が材料に食い込んで跳ね返る現象)のリスクが比較的低いとされています。そのため、電動工具を初めて使う方でも比較的安全に扱いやすい工具と言えるでしょう。
また、先端のブレードを交換することで、木材から金属、プラスチックまで幅広い素材に対応できる汎用性の高さも魅力の一つです。解体作業からDIY、庭木の剪定まで、プロの現場から家庭での使用まで、非常に幅広いシーンで利用されています。
レシプロソーとセーバーソーの違いは?

結論から言うと、レシプロソーとセーバーソーは基本的に同じものを指しており、機能的な違いは一切ありません。
では、なぜ2つの呼び方が存在するのでしょうか。その理由は、メーカーによる商品名の違いにあります。例えば、電動工具大手のマキタやパナソニックは「レシプロソー」という名称で製品を販売しています。一方で、HiKOKI(ハイコーキ)やボッシュといったメーカーは「セーバーソー」という名称を使っています。
呼び名の由来
前述の通り、「レシプロソー」は往復運動(reciprocating)が語源です。一方、「セーバーソー」の「セーバー(saber)」は、剣の一種であるサーベルを意味し、その細長い刃の形状から名付けられたと言われています。世界的には「レシプロソー」が一般的な呼称です。
このように、呼び方が違うだけで工具としては同一のものですので、どちらの名前で探しても問題ありません。近年はマキタの市場での人気から「レシプロソー」という呼び方がより広く浸透してきている傾向があります。
レシプロソーは何に使う?主な用途

レシプロソーの最大の特徴は、そのパワフルさと汎用性の高さにあります。具体的にどのような場面で使われるのか、主な用途を見ていきましょう。
解体作業
レシプロソーが最もその力を発揮する分野です。家屋の解体現場では、壁や床、天井などを壊す際に、釘が刺さったままの木材や金属製の配管などをまとめて切断できます。他の工具では難しいような、複雑な構造物もパワフルに破壊・分解していくことが可能です。
設備工事
電気工事や水道工事の現場で、塩ビ管(PVCパイプ)や金属管の切断に使われます。狭い場所や設置済みの配管を切断する際に、そのコンパクトさと取り回しの良さが役立ちます。
庭木の剪定
手ノコギリでは大変な太い枝の剪定も、レシプロソーを使えば簡単に行えます。チェンソーほど大掛かりではなく、手軽に使えるため、庭の手入れに活用する方も増えています。
粗大ごみの解体
家庭で出る不要になった家具やカーペット、プラスチック製品などを細かく解体し、普通ごみとして処分したい場合にも非常に便利です。処分費用を節約できるというメリットもあります。
このように、レシプロソーは「作る」というよりは「壊す・切る・解体する」といった、ラフな切断作業を得意とする工具と言えますね。
レシプロソーで切れるもの一覧

レシプロソーの大きな魅力は、先端のブレード(替え刃)を交換するだけで、非常に多くの種類の素材を切断できる点にあります。適切なブレードを選べば、以下のような様々なものを切ることができます。
| 分類 | 具体的な素材例 |
|---|---|
| 木材 | 一般木材、角材、コンパネ、竹、庭木の枝など |
| 金属類 | 鉄管、ステンレス管、アルミサッシ、アングル、鉄筋など |
| 樹脂類 | 塩ビ管(PVC)、プラスチック製品、FRP(繊維強化プラスチック)など |
| 複合材 | 釘やビスが入った木材、断熱材が入った壁など |
| 窯業系建材 | ALC(軽量気泡コンクリート)、サイディングボード、石膏ボードなど |
注意点
切断する素材の厚みや硬さに合ったブレードを選ぶことが非常に重要です。不適切なブレードを使用すると、切れ味が悪いだけでなく、ブレードの破損やモーターへの過負荷につながり、工具本体の故障原因にもなりますので注意しましょう。
レシプロソーはジグソーの代わりになる?

結論として、レシプロソーがジグソーの完全な代わりになることは難しいと言えます。
ジグソーもレシプロソーと同じく、ブレードを上下(または前後)に動かして材料を切断する電動工具です。しかし、その設計思想と得意な作業が根本的に異なります。
ジグソーの特徴
ジグソーは、本体下部に「ベースプレート」という平らな土台が付いています。これを切断する材料にしっかりと押し当てることで、ブレードを安定させ、正確な切断を可能にします。この構造により、曲線切りや板材のくり抜き(窓抜き)といった、繊細で精密な作業を得意としています。
レシプロソーとの役割の違い
一方、レシプロソーには大きなベースプレートがなく、パワーとスピードで大まかに切断していく「ラフカット」が専門です。そのため、ジグソーのような綺麗な切断面や正確な曲線加工は期待できません。
使い分けのまとめ
- ジグソー:綺麗な切断面、正確な直線・曲線切り、板のくり抜き作業(DIYでの家具製作など)
- レシプロソー:パワフルな切断、解体、剪定、精度を問わない粗切り(粗大ごみの分解など)
このように、両者は似ているようで全く異なる役割を持つ工具です。もし一台で様々なDIY作業をこなしたいのであれば、細かい作業に対応できるジグソーの方が汎用性は高いと言えるかもしれません。
レシプロソーとチェンソーの違いを解説

レシプロソーとチェンソーは、どちらもパワフルな切断工具ですが、その切断メカニズムと主な用途には大きな違いがあります。
切断の仕組み
- レシプロソー:一本のノコギリ刃が前後に往復運動して切断します。
- チェンソー:たくさんの刃が付いたチェーンが、ガイドバーの周りを高速で回転して切断します。
得意な作業と対象物
チェンソーは、太い木や丸太の切断に特化したスペシャリストです。木の伐採や薪作りといった作業では、その回転力を活かした圧倒的なスピードで木材を削り取っていきます。しかし、その用途はほぼ木材に限られ、金属や釘などが混ざった材料を切ることはできません。
対してレシプロソーは、多種多様な材質に対応できるジェネラリストです。前述の通り、ブレードを交換すれば木材はもちろん、金属やプラスチックも切断可能です。太い木の切断スピードではチェンソーに劣りますが、木材と金属が混在する解体作業や、狭い場所での枝打ちなど、より幅広い場面で活躍します。
安全性に関しても違いがあります。チェンソーはキックバックが発生すると非常に危険ですが、レシプロソーは比較的そのリスクが低く、扱いやすいという側面も持ち合わせています。
庭木の剪定程度であればレシプロソーで十分対応できますが、本格的な伐採作業にはチェンソーが必要、というように目的によって明確に使い分けることが重要です。
実践編!レシプロソーとはどう選ぶ?
- 後悔しないレシプロソーの選び方
- 用途で変わる替え刃の種類と選び方
- レシプロソー使い方のコツと注意点
- おすすめレシプロソーのメーカー4選
- まとめ:結局レシプロソーとはどんな工具?
後悔しないレシプロソーの選び方

レシプロソーを選ぶ際には、ご自身の用途に合ったモデルを見つけることが重要です。チェックすべきポイントは主に「動力源」と「切断能力」の2つです。
動力源で選ぶ
レシプロソーの動力源は、大きく分けて「充電式」と「コード式」の2種類があります。
- 充電式(バッテリー式)
電源コードがないため、取り回しが非常に良く、コンセントがない屋外や高所での作業に最適です。現在の主流はこちらのタイプで、バッテリーの性能向上によりコード式に引けを取らないパワーを持つモデルも増えています。ただし、バッテリーと充電器が必要なため初期コストが高くなる点と、稼働時間がバッテリー容量に依存する点がデメリットです。 - コード式(AC電源)
コンセントから直接電力を供給するため、バッテリー切れの心配がなく、長時間の連続作業や安定したパワーが必要な場面で力を発揮します。また、バッテリーなどが不要な分、本体価格が比較的安価なのも魅力です。一方で、電源コードが届く範囲でしか使えず、作業中にコードが邪魔になる可能性があるのが難点です。
切断能力で選ぶ
製品の仕様には「最大切断能力」が記載されており、これはそのモデルがどれくらいの太さの材料を切断できるかの目安を示しています。(例:パイプ130mm、木材255mm)
切断能力の目安
- ~50mm:DIYや家庭での粗大ごみ解体、細い枝の剪定など、軽作業向けのコンパクトモデルに多い能力です。
- 130mm前後:最も一般的なクラスで、製品ラインナップも豊富です。プロの設備工事から本格的なDIYまで幅広く対応できます。
- 150mm以上:プロ向けのハイパワーモデル。太い鋼管や建物の梁など、ヘビーな解体作業に対応します。
ご自身が「何を使って」「何を切りたいのか」を明確にすることで、最適な一台を選ぶことができるでしょう。
用途で変わる替え刃の種類と選び方

レシプロソーの性能を最大限に引き出すには、切断する材料に最適なブレード(替え刃)を選ぶことが不可欠です。ブレードは消耗品であり、様々な種類が販売されています。
ブレードの互換性について
レシプロソーのブレードの取り付け部分は、マキタ、HiKOKI、ボッシュ、京セラなど、ほとんどのメーカーで共通の規格(ユニバーサルシャンク)になっています。そのため、本体とブレードのメーカーが異なっていても問題なく使用できるのが大きなメリットです。
ブレードを選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。
材質で選ぶ
切断したい対象の素材に合わせて選びます。
- 木工用:木材や竹、剪定などに。刃が粗く、切断スピードが速いのが特徴です。
- 金属用(鉄工用):鉄やステンレス、アルミなどの切断に。刃が細かく、硬い素材に対応します。
- 解体用(バイメタル):釘の入った木材など、木と金属が混在した材料の切断に最適です。
- ALC・窯業用:ALCやサイディングボードなどの切断に使われます。
山数(TPI)で選ぶ
山数(TPI: Teeth Per Inch)は、1インチあたりの刃の数を示します。
- 山数が少ない(刃が粗い):切断スピードは速いが、切断面は粗くなる。(木材など柔らかい素材向き)
- 山数が多い(刃が細かい):切断スピードは遅くなるが、切断面は綺麗になる。(金属など硬い素材向き)
その他、切断したい材料の厚みに合わせた「長さ」や、耐久性に関わる「厚さ」も選ぶ際の重要な要素となります。
レシプロソー使い方のコツと注意点

レシプロソーを安全かつ効率的に使うためには、いくつかのコツと注意点があります。特に初心者の方は、使用前に必ず確認してください。
シューをしっかり押し当てる
これが最も重要なポイントです。「シュー」とは、ブレードの根元にある金属製のガイド部品のこと。ここを切断する材料に常にしっかりと押し当てて作業してください。
シューを押し当てないとどうなる?
シューが材料から浮いた状態でスイッチを入れると、本体が激しく振動し(暴れ)、非常に危険です。切断効率が著しく落ちるだけでなく、ブレードが折れたり、材料や本体を破損させたりする原因になります。振動を材料に伝えるイメージで、体重をかけて押し付けましょう。
両手でしっかり保持する
レシプロソーは振動が大きい工具です。片手で作業すると制御が難しく危険なため、必ず両手で本体をしっかりと握って操作してください。
切断時の注意点
- 切断開始時:いきなり最高速で刃を当てるのではなく、低速で少し切り込みを入れてからスピードを上げると安定します。
- 材料の固定:切断する材料が小さい場合や不安定な場合は、クランプなどでしっかりと固定すると安全に作業できます。
- 保護具の着用:作業中は、切粉や破片から目を守るための保護メガネ、振動や切り口から手を守る作業用手袋を必ず着用しましょう。
特に金属を切断する際は、火花は少ないものの高温の切粉が飛ぶことがあります。安全第一で作業を進めることが大切ですね。
おすすめレシプロソーのメーカー4選

どのメーカーのレシプロソーを選べばよいか迷う方のために、信頼性が高く人気のある主要メーカーを4社ご紹介します。
マキタ(Makita)
国内トップシェアを誇る電動工具メーカー。豊富なラインナップと、バッテリーの互換性の高さが最大の魅力です。プロ向けのハイパワーモデルからDIY向けのコンパクトなモデルまで幅広く展開しており、多くのユーザーから支持されています。特に充電式モデルの性能には定評があります。
ハイコーキ(HiKOKI)
旧日立工機。独自の高出力バッテリー「マルチボルトシリーズ」が特徴で、パワフルさと高い技術力でプロユーザーから根強い人気があります。製品の耐久性も高く、ハードな現場での使用にも耐える堅牢な作りが魅力です。セーバーソーという名称で販売しています。
ボッシュ(BOSCH)
ドイツ発祥の世界的な電動工具メーカー。安全性を第一に考えた製品開発を行っており、ブレード交換が簡単な「SDSシステム」などを先駆けて開発しました。プロ向けの「ボッシュブルー」シリーズは、その高い品質と耐久性で世界中の職人から信頼されています。
京セラ(KYOCERA)
旧リョービのパワーツール事業を承継。DIYユーザーや初心者でも扱いやすい、コストパフォーマンスに優れたモデルを多くラインナップしています。操作が簡単で、家庭での使用を想定した便利な機能を搭載した製品が人気です。
まとめ:結局レシプロソーとはどんな工具?
最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。
- レシプロソーとはブレードを往復させて切断する電動のこぎり
- セーバーソーとはメーカーによる呼び方の違いで同じ工具
- 主な用途は解体、配管切断、剪定、粗大ごみの分解
- ブレード交換で木材、金属、プラスチックなど多様な素材に対応
- ジグソーは精密な曲線切り、レシプロソーはパワフルな粗切りと役割が違う
- チェンソーは木材専用、レシプロソーは多材質対応の汎用性が強み
- 選び方の基本は動力源(充電式 or コード式)と切断能力
- 充電式は取り回しが良く、コード式はパワーと連続作業に優れる
- ブレードは材質と山数(TPI)を切断対象に合わせて選ぶことが重要
- ブレードの取り付け規格は多くのメーカーで共通化されている
- 使い方の最大のコツはブレード根元のシューを材料に強く押し当てること
- 作業時は振動が大きいため両手でしっかり保持し保護具を着用する
- 代表的なメーカーはマキタ、HiKOKI、ボッシュ、京セラなど
- ご自身の用途と予算に合ったモデルとブレードを選ぶことが後悔しないコツ